
「突然名前のない手紙が来ました。中には『ありがとう』とだけ書いてあります。さて、差出人は誰でしょう?」「親、昔の恋人、友人、見知らぬ人のうちどれだと思いますか?」
「好きなアイスクリームは?」「バニラ、チョコ・・・」
それぞれ手を挙げていきます。そのこころは・・・
こんな心理テストを何問かやっていました。生徒たちは、目を輝かせて取り組んで?いました。
入学試験の結果や来週に迫った前期選抜など、少し追い込まれている様子の生徒たちでしたが、少しの時間でもこんな時間があると表情が明るくなりました。
入試の期間は、きっと今まで生きてきた中で一番心不安な日々だと思います。緊張ばかりでは疲れてしまうので、ホッとしたり笑ったりする時間を大切にして乗り切りましょう。








2025年02月1日 |カテゴリー:3年生

緊張する面接練習は3階の少人数教室で行われます。終わった生徒は「ボロボロだった。もっと調べて将来のことも考えないといけない。」と反省しきり。
面接練習以外の生徒たちは教室で自習。塾の問題集をしたり昨日行われた試験問題の答え合わせをしたりと、それぞれ頑張っていました。
多くの生徒が私立の試験を受けたので、入学試験の緊張感や問題の難解さを実感できたようで、明らかに今までとは違う様子。友だちと教え合うときも熱意があふれています。
今が一番しんどい時ですが、教室の雰囲気はなぜか楽しそうです。同じ境遇の仲間といると、心強いですね。








2025年01月29日 |カテゴリー:3年生

先週の金曜日から一週間は給食週間、人気の献立が続きます!今日はみんな大好き「唐揚げ」。準備をする給食当番も色めき立っていました。
さて、給食週間の初めの2日間3年生は受験のため給食カットでした。そしてその2日間の献立は「揚げパン」「カレー」いう事実を献立表で知った生徒たち。
落ち込む生徒が少なからずいました。(もしかしてもう揚げパンは食べられないのかもしれない)という思いで、ちょっぴり残念そうに給食準備をしていました。




2025年01月29日 |カテゴリー:3年生

今日も私立の入試に多くの生徒が行っています。教室は少し寂しい状態です。
授業も自習がメインで、1、2年生とは違う雰囲気の3年生でした。


2025年01月27日 |カテゴリー:3年生

3限目の授業が終わって・・・
帰り学活が終わったクラスから、帰る用意をする生徒たち。3限しかないので持ち物も少なくあっという間に準備がおわり、教室を出る合図のチャイムが鳴るまで扉の前で並んで待っていました。
黒板にある卒業式までのカウントダウンカレンダーを一日進める作業をする生徒もいました。
明日からは通常日課です。給食当番がエプロンを持ってくるか心配です!




2025年01月27日 |カテゴリー:3年生

卒業制作の堆朱が進んできました。層を出す段階までいった生徒も出てきて、カラフルになってきました。磨く作業をしっかりするとピカピカになって、売り物?と思ってしまうようなキーホルダーになります。頑張りましょう。
この作品が最後なので席を自由にして楽しみながら進めています。美術は楽しみながら進めると作品にも反映するものです。中学校最後の作品制作を存分に楽しみましょう。






2025年01月24日 |カテゴリー:3年生

受験シーズンで一番怖いのが感染症。各自手洗いを心掛けてくれていますが、教室の換気も大切。
今は一年で一番寒い時期ですが、廊下側と反対のグラウンド側の窓は少し開けて、風が通るようにしています。
また、コロナの時に購入した空気清浄機も活躍中。
みんなが安心して過ごせるように対策されています。

2025年01月23日 |カテゴリー:3年生

ASCの後は朝学活です。班で担当する司会係が前に出て進めていきます。
メインは健康観察と今日の予定の確認。受験対応などで時間割変更が頻繁にあるので、情報を見逃さないように共有していきましょう。

2025年01月23日 |カテゴリー:3年生
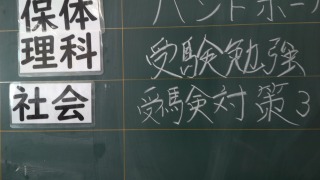
受験WEEK。授業も受験体制になっています。
ウィークポイントやもう一度やりたいところなど、各自ポイントを決めて黙々と取り組む姿が見られました。
受験を終えただけではなく、その結果が出た生徒もでてきました。気付けは受験の真っただ中の3年生。切羽詰まった時は、いつも以上に集中できたり力が出たりするものです。この緊張感を上手に使って最後の追い込みを頑張りましょう。










2025年01月22日 |カテゴリー:3年生

ハンドボールのボールとコートを使って、オリジナルハンドボールをしました。本当のハンドボールではなく、自分たちで楽しくできるようなルールを作りました。
移動の時のドリブルはないようなので、4歩以上歩いてもOK。中にはパスを受けてそのままゴール前までダッシュしシュート!のような楽しいプレーも見られました。
声を掛け合ったり一緒に喜んだり、チームが一体になる感覚が嬉しい。仲間とのつながりを育む楽しい時間でした。












2025年01月22日 |カテゴリー:3年生